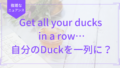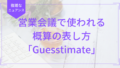英語の「Termination for Convenience」という言葉を訳すと、「任意解約」になります。
これは法律用語なのですが、
堅い書面の中に「Convenience」という言葉が入っているため、
初見の場合、ちょっとびっくりするかもしれません。
「Convenience」と聞くと、私たちはついどこにでもある
「コンビニ(Convenience Store)」を連想しがちです。
ちなみに、アメリカでもヨーロッパでも、コンビニは「Convenience Store」と呼ばれています。
では、終了や解雇などを表す「Termination」と
コンビニエンスが混じった「Termination for Convenience」というこの言葉は、
どういった場面で使うのでしょうか?
店舗のコンビニとは違うんだろうな、と思いながらも、
「何かしらの契約を、コンビニを利用する感覚で、気軽に解約できるの?」
この発想は、あながち間違いではありませんでした。
「Convenience」には、知っている方も多いとおり、「便利」という意味があります。
「Termination for Convenience」として使う場合は単純に
「便利」という使われ方ではなく、
「特に理由はないけど、やめたくなった時の都合で」
「契約上、相手に非がなくても、自分の事情で自由に解約できる」
というニュアンスが、含まれます。
直訳すると「便利のための解約」
ですが、実際は「契約違反や相手のミスがなくても、
一方的に解約できる条項」という意味になります。
つまり、「気が変わったら解約OK!」という、
まるで悪魔のような契約解除権なんです。
まさにコンビニ感覚の、気軽な解約。
「こんな契約、本当にあるの?」
と思うかもしれませんが、実際に存在しています。
特に多いのが、政府相手の契約です。
一例ですが、東南アジア政府と契約する場合、政府の権限が非常に強いため、
「やっぱりこのプロジェクトいらなくなったから契約解除ね!」
といった手のひら返しが普通にありえます。
民間企業であれば、
「そんな勝手な話あるか!」
と裁判沙汰になりそうな場面ですが、相手が政府となると……どうしようもないですよね。
契約解除されないように、慎重に話を進めたり、
絶対必要だと思われるアイデアを出したりするしかなさそうです。
相手が変われば、ビジネスの常識も変わるもの。
海外相手に契約する場合は、
書面などに「Termination for Convenience」という文字が含まれていないか、
要注意ですね。