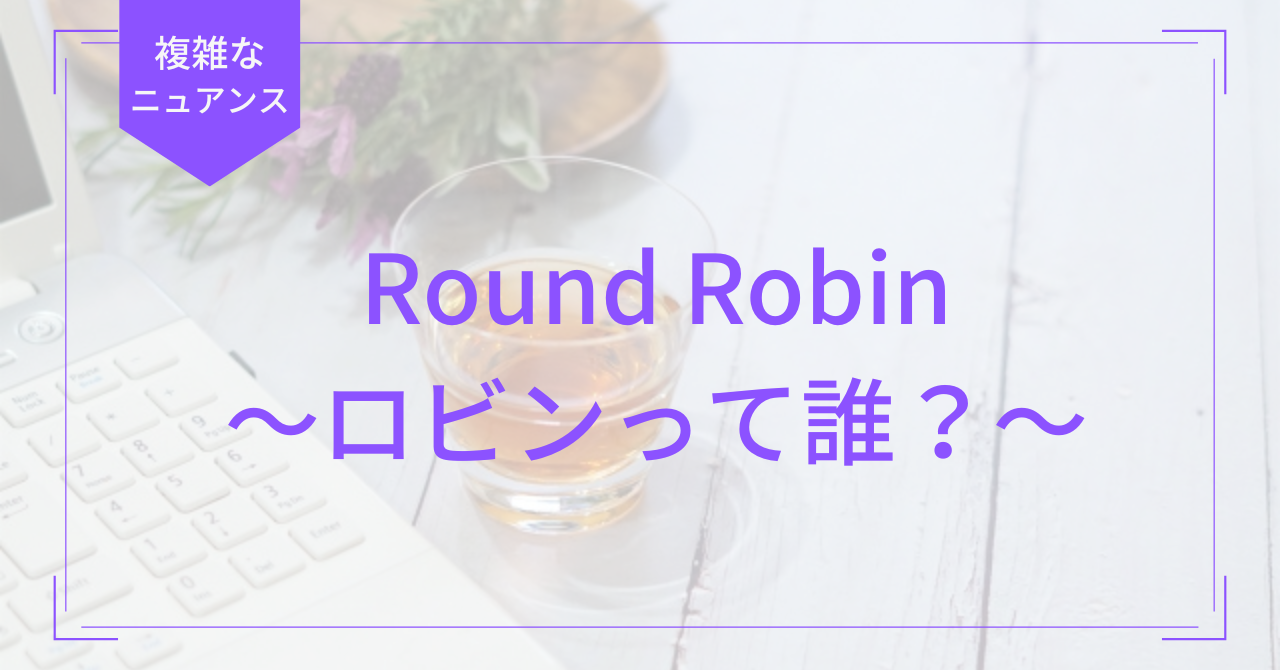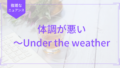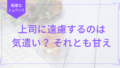みなさんは「go around the horn」って言葉、聞いたことありますか?
これは、会議やディスカッションで耳にするフレーズなのですが、最初に
「Let’s go around the horn」
と言われたときは、
「horn(ホーン)って何? 動物のツノ? 何のツノ?」
と戸惑いました。
意味は分からないけれどなんとなく、
「みんなで丸いテーブルを囲んで、ツノが曲がるみたいに順番に話していく?」
みたいなイメージが頭に中に湧きあがり、
その場は納得したのを覚えています。
この解釈、単なる思いつきだったのですが、
あとから調べたところ、ビジネス英語としての意味は間違っていませんでした。
「go around the horn」は
「順番に話す・一人ずつアップデートを話す」という意味があり、
日ごろから頻繁に使われています。
ですが本来は、まったく別の意味で使用されていました、
私ははじめ、ホーンの意味をツノだと解釈しましたが、
もともとの「Horn」は南アメリカ最南端にある「ケープ・ホーン(Cape Horn)」という、
海の難所を指すそうです。
パナマ運河ができる前、ヨーロッパからアジアに行く船は、
南米を抜ける必要があり、嵐の多い危険な岬、
すなわち「ケープ・ホーン(Cape Horn)」をぐるっと回らなければいけませんでした。
この事実から、
「go around the Horn」=「わざわざ遠回りをする」「危険で手間のかかるルートを通る」
という意味合いで使っていたとのこと。
つまり、「go around the horn」には、
- ビジネス会議では「順番にアップデートを言おう」
- 航海由来の意味では「危険な大回りルートを通る」
という、2つの意味が混在しているんですね。
ケープ・ホーンを船で順番に回っていく、という意味が転じて、
順に話すに変わっていったのかもしれません。
「順番に話す」という表現には、
「Round Robin(ラウンドロビン)」「Let’s go round the Robin」という言葉もあります。
これは、「go around the horn」と同じで
「順番に意見を出していこう」といった声かけをしたいときに使われます。
ただどちらかというと「順番に」というよりも「順繰りに」ということに
ニュアンスの重きがあります。
そのニュアンスがよく出ているものでは
スポーツのリーグ戦で「総当たり戦」を意味する
「 Round Robin Format」という言葉もあります。
仕事の現場では「当番制で回す」「順繰りに処理する」などの文脈でも、
よく登場するフレーズです。
このRound Robin
「ロビンって誰?」
「ロビンを回るってどういうこと」
そんな風に思った方、いると思います。
私も不思議に思ったのですがこのRobinの由来、実は人名ではありませんでした。
そもそもの語源は、17世紀のフランス語、 rond ruban(円形のリボン)です。
円形のリボンのように、署名を輪の形に並べ、
誰の意見か分からないようにした状態で、
責任や主張を平等に共有するというスタイルを指しています。
「順番に」「みんなで公平に」「一人に負担を偏らせない」といった、
協力と分担の象徴として、使われてきたフレーズなんですね。
参加者のためを思って生まれたRound Robinの習慣。
ですが、現代の働き方やチームワークの話になると、
私は「バットマンとロビン」のRobinの方が思い出されます。
「Playing Robin to someone’s Batman
(誰かのバットマンに対してロビン役を務める)」
というフレーズがあるのですが、
こちらは「主役を支える信頼できる相棒」という意味で使われます。
企業においては「Round Robin」でみんなが声を出し合い、
順番に役割を果たす。
そして時には「バッドマンのためのロビン」になって、
リーダーを支える存在になる。
そんな2つのロビンで動く関係を作れると、チームがもっと強く、しなやかになっていきそうです。