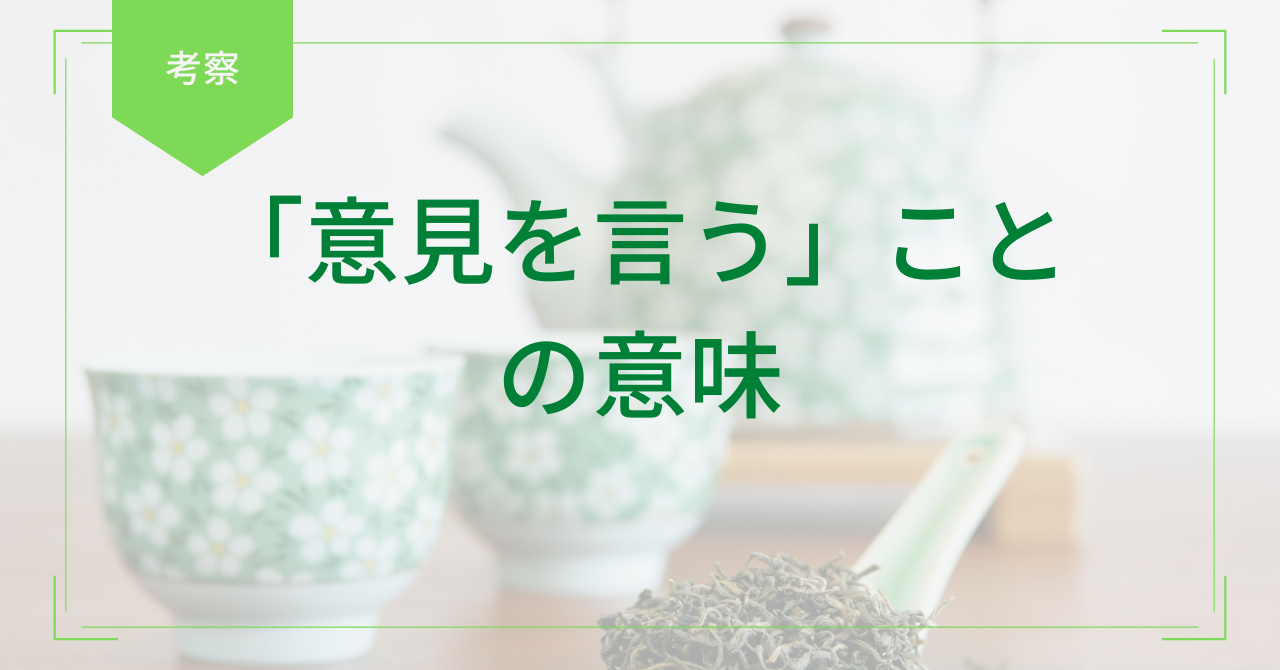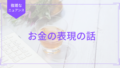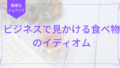ビジネスの現場では、「意見を言う」という行為は、
あらゆる場面で求められます。
一方で、「意見を言う」姿勢や、
その後の責任の取り方は、国や文化によって大きく異なります。
日本で育った私は、グローバルな環境で働くようになってはじめて、
解釈の違いを体感しました。
今回は日本とアメリカを例に、意見が持つ意味や考え方を解説いたします。
日本では「意見を言う」行動そのものが評価される
日本には、昔から「報連相」という文化があります。
また会議やプロジェクトの場においては、
積極的に意見を述べる“行動自体に価値がある”と評価されます。
状況を正しく伝えるために、
上司やリーダーへ問題や課題を共有する、会議の場で意見を伝える、
といった行為が、重要な意味を持っています。
意見を述べた後のアクションや責任については、
部下からの言葉を受け取ったリーダーや上司、会社などの判断に委ねられるのが一般的です。
意見を出した担当者が、その後の行動や解決案まで考え伝えるのは、
でしゃばる印象が強くなるため、あまりみられません。
日本独特の稟議制度のように、
意見を上げたあとは上層部の決裁を待つ、という流れが多く
「声を上げること」と「責任を持って動くこと」は、別の行動として捉えられています。
アメリカでは「意見=行動」が前提
外資系の企業ではたらいてみて、日本と大きく違うと感じたのが、
「意見=行動」が前提になっている文化です。
アメリカの職場では、仕事を進める上で
「あなたはどうしたいの?」「あなたは何をやるの?」とよく聞かれます。
そのため、意見を言うだけでなく
“実現するために自分は何をするべきか”という点を考えておく必要があります。
意見を出すのは当たり前で、もちろん歓迎される行為なのですが、
「行動」や「提案」が伴っていなければ評価されません。
また自分の意見の責任は、上司や会社ではなく、基本的に自分自身です。
日本のように、気になった部分や問題点を指摘するだけでは
「批判的」だと受け止められてしまう可能性が高いため、注意が必要です。
また意見だけを述べた場合には、
「では、あなたはこの問題をどう解決するつもりなのか」
と追求されるため、意見をもとにした具体的な施策、行動の提案が欠かせません。
英語圏で仕事をはじめたばかりの頃、
意見を言うとどんどん仕事が増えてしまうため、
「対応できないなら、黙っておいた方がいいってこと?」
と腐ってしまいそうでした。
ですが次第に、「意見を言う=責任を負う」というアメリカ式の考えを、
柔軟に捉えられるようになりました。
会社の課題は、大きいものから小さいものまであり、
すべてを自分一人で解決できる訳ではありません。
そのため現在は、「意見を出す時に、自分ができる範囲での改善策や次の一手を添える」
という言動を心がけています。
自分では責任を負えない内容については、
専門性のある人材を紹介する、協力しながら進められるようにレポートを書いて共有する、
といった風に、できる協力、できる範囲に限ってしまうけれども、何らかの協力を惜しまない形です。
小さいアクションしかできないケースもありますが、
「自分なりに考えていること」を伝える、「自分が実行できること」を精一杯やる、
これだけで、相手の心象が大きく変わります。
これから外資系ではたらく予定がある方は、ぜひ試してみてください。
文句を言うこと=改善のスタート地点
海外相手の会議や相談に耳を傾ける場合、やってはいけない行動があります。
それは「責任が伴うなら、文句や不満を言うのは止める」という極端な選択です。
なんらかの文句や不満が生まれたら、
その気持ちを「問題改善に向けた具体的な提案」や「前向きな意見」に変えていくと、
建設的なコミュニケーションにつながります。
日本では、文句や不満ばかり言っていると敬遠されます。
ですがアメリカでは、問題を解決するための意見や提案、
変えていく姿勢を見せる行為は“文句や不満を持つ以上の意味がある”と考えます。
「やりたくないから黙っている」という行動を選んだ場合、
チームや自分自身の成長機会を逃す結果につながってしまいます。
不満や文句ある、ということは、改善のスタート地点に立っている、ということ。
外資系や英語圏での業務で気になった部分、
変えていきたい部分があれば、自分にできる提案やアクションを添えて、
意見を声に出してみてください。その一声が、相手との良い信頼関係作りにつながるはずです。