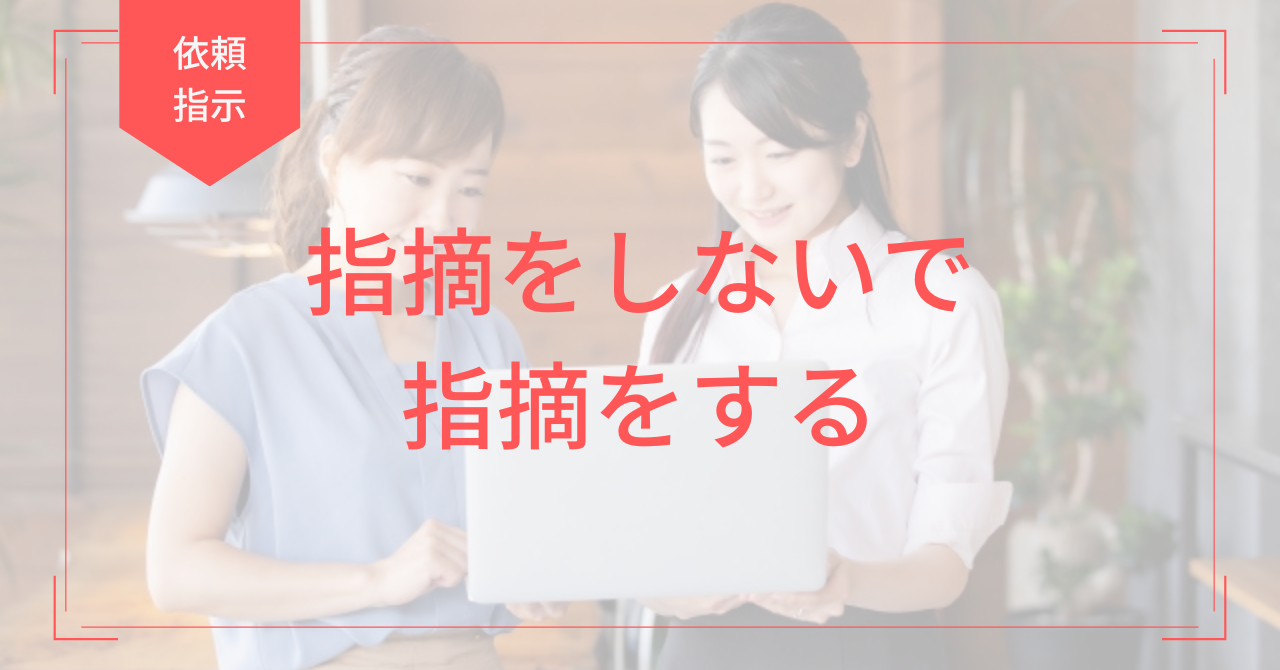「指摘をしないで指摘をする」
と聞いて、どんな場面が思い浮かびますか?
たとえば、新人医師が診察や処置をしていて、判断を間違えそうなとき。
その場にいたベテラン看護師が「それは間違っていますよ」と指摘する行為は、
新人医師のプライドを傷つけてしまう可能性があるため、NGとされています。
それでは、ベテラン看護師は、どのような言葉で間違いを伝えるのでしょうか?
「指摘をしないで指摘をする」工夫の例をみてみましょう。
仮に、新人医師が患者を診察していて、投与する薬の量を間違えそうだったとします。
このときベテラン看護師は、「薬の量が間違っていますよ」と言わずに、
「○○mgで進めますよね?」と聞くそうです。
この言い方なら、新人医師がはじめから正しい量で投与しようとしていた印象になり、
「そうだね」と自然な形で修正・訂正を完了できます。
目の前に患者さんがいる場合も、この言い方なら不安にさせません。
ベテラン看護師と医師の例のように、
経験豊富なスタッフが相手の立場を考えた上で、プライドを守りながらサポートする、
現場でのスムーズな協力体制を築いていく、という構造は、
企業の中でも目にします。
業務の中で「さりげなく正しい道を示す」アプローチができれば、
相手の精神的な負担を減らせるため、信頼関係を保ちながら、物事を進められる点がメリットです。
- 「〇〇さんに許可を取らないで、進めたらダメですよね?」
ではなく、
- 「この提案は、〇〇さんにご確認を入れてから進めればいいですか?」
と尋ねる。
- 「出張先で必要になるからXXの資料を読んでおいてください」
ではなく、
- 「出張前に事前資料として、XXをご用意しましょうか?」
と申し出るなど、
相手に“Yes, please” で回答できるような質問形式で尋ねるという
ちょっとした工夫で、受け取る側の気持ちに寄り添えます。
英語で伝える場合は、
- Would you like to?
- Shall we?
などのフレーズを活用して、提案型の会話を選ぶのがおすすめです。
- You should…
- You need to_
といった言葉は、相手の間違いや見落としを指摘する形になり、
偉そうな印象になってしまいます。
「指摘をしない指摘」は、仕事だけでなく、
友人関係や家族関係にも広く使えるテクニックですので、ぜひ実践してみてください。