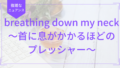「Cutting board」と「Chopping Board」という言葉。
これはどちらも、日本語に訳すと「まな板」です。
二つとも、キッチン用品の名称としてイメージしやすい言葉ですが、ビジネスの場面では、
- The email alert is on the chopping board already.
- (そのメール警告は、すでに停止の検討対象になっている)
このような形で使われるケースがあります。
この例では、「Chopping Block」が使われていますが、
キッチンにあるまな板は、「Cutting Board」と呼ぶのが一般的です。
英語圏でもし、家庭用のまな板を「Chopping Block」と表してしまったら、
聞いた相手はギョッとしてしまうかもしれません。
なぜかというと、まな板の中でも「チョッピングブロック」と呼ばれる商品は、
より厚くて重い木製のアイテムだからです。
「Chopping Block」が活用されるのは、
肉屋や飲食店などが多く、大きな肉の塊や、骨付きの肉を切るために使われています。
Chopping Block=中華料理屋で使われている、
大きくて重たい中華包丁と一緒に見かける、巨大で重たい木製のブロック、
という印象になり、家庭的ではありません。
一方の、「カッティングボード」は、私たちが普段から家で使用する、
薄めのまな板を指します。
小さな包丁で切れるサイズの肉や魚、野菜、パンなどを切るのが仕事です。
プラスチックや竹、木材など、軽い素材が用いられています。
「チョッピングブロック」という言葉は、
その大きくて重たい印象からか、料理以外でも広く使われます。
先ほどの事例は、「処分対象」や「削減候補」といった、比喩的な活用方です。
他にも、「チョッピングブロックに乗る(on the chopping block)」という言葉が有名です。
これは、「(人や物が)切られる・排除される危機にある」という表現になります。
願わくば、乗りたくない恐ろしい場面ですよね。
イメージや解釈の違いを防ぐためにも、
外国人の私たちは使用を控えた方が良い表現な気がします。
日本語にも、まな板を使った、「まな板の鯉」ということわざがあります。
ChoppingBlockに乗る、と似ていますが、
「まな板の鯉」は少し意味が違って、すでに運命が決まっており、受け入れるしかない状態を表します。
以前、海外の人を相手に、
「もう、まな板の鯉だな……。詰んだ……」
という表現をしたい場面がありました。ですが、ただでさえ詰んでいるのに、
まな板の鯉はどう表せば?
と訳のわからない悩みを抱いたのを覚えています。
英語で、冷静に運命を受け入れる、という気持ちを指すなら、
「So be it.(そうなるならそうなれ)」でしょうか。
これは、会社でも日常でも、割と良く耳にする言葉です。
投げやりなイメージに聞こえますが、
どちらかというと無責任と言うよりは、
「やるしかない、しょうがない」というニュアンスです。
まな板の鯉よりは、ちゃんと覚悟を決めた状態になり、多少ポジティブな印象になります。
「もう逃げ道がない」という状態を強調したい場合は「No way out」 という表現があります。
- We’re in deep trouble—there’s no way out.
- (問題が深刻で、もう逃げ道がない)
出口のない困難な状況に置かれている、という心理的圧迫感を伝えるのに効果的ですが
……英語でビジネスをしている限り、この言葉はできるだけ使いたくないですね。