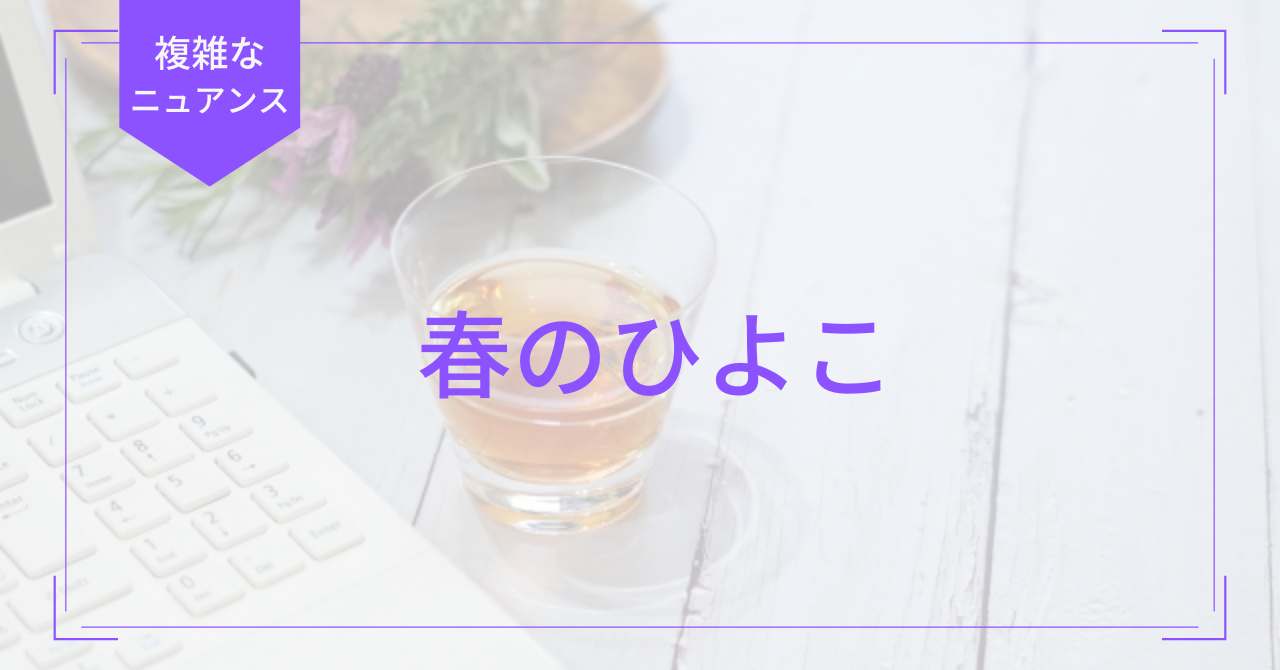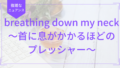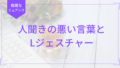先日、一緒に仕事をしているPaulと話していたとき、彼の口から、
- 「He is not a spring chicken any more!」
そんな言葉が飛び出しました。
これ、直訳すると「もう春のひよこじゃない」という意味ですが、
私たちは季節によって違う、ひよこのイメージを持っておらず……
ちょっと意味が分からないですよね。
彼の言葉は、実は英語のイディオムで、
「もう若くない」「若い頃のようにはいかない」というニュアンスで使われていました。
日常会話の中で、軽い冗談として使われるケースが多いフレーズです。
彼は、その場を和ませながら
「相手さんはおじ様だから、配慮しようね」といった含みを持たせたかった、という一件です。
ではなぜ、「若くない=春のひよこじゃない」なのでしょうか?
“spring chicken” の “spring” はそのまま、「春」という季節の意味で用いられています。
春は命が芽吹き、動物が生まれ、
エネルギーに満ちた季節のため、「春のひよこ=若くて元気な存在」というイメージで、
このイディオムが生まれました。
英語の表現をみてみると、
他にも「春」という言葉に、元気さ、若さ、活力を象徴している例が多くあります。
実際のフレーズを、いくつかみてみましょう。
“Spring into action”
「すぐ行動に移す」という意味があります。春の陽気の勢いで、
ぱっと動き出すイメージで使われています。
“A spring in your step”
「足取りが軽い」つまり、気持ちが弾んでいる状態を指します。
春だからお出かけしたくなる、新しいことにチャレンジしたくなる、そんな光景が浮かびます。
“Spring fever”
「春の陽気で、気持ちが落ち着かない状態」です。
春になった開放感でいっぱいになり、心がそわそわする感じを表現しています。
“Hope springs eternal”
「希望が永遠に湧き上がる」という意味です。
どんな状況であっても、人は希望を持ち続けられる、という力強い意志を示しています。
このように、「春(spring)」という言葉は、
英語のイディオムにおいて、「活力」や「希望」の象徴として根付いています。
ところで、“spring” にはもう一つ、「バネ」という意味もありますよね。
最初に、「Spring Into Action」「 A spring in your step」という言葉を聞いたとき、
私はバネの方を指しているのかと思いました。
バネを表す方の“spring”には「跳ねる」「弾む」という動きそのものを示す言葉です。
そのため、バネだと解釈しても、
「コイルのように力を溜めて一気に跳ねる」という元気な様子をイメージできます。
バネが語源のフレーズである “spring back” は
「元に戻る」「跳ね返る」という意味で使われています。
押しても元に戻るバネの性質から、バネのように戻る、跳ね返る、というイメージが由来です。
つまり「spring」は、バネの意で活用する場合も、
停滞せず、動き出すエネルギーの象徴というイメージなんですね。
綴りは同じ単語だけど、まったく違う意味。
それなのに、どちらの解釈でもイディオムが通じてしまう。
考えてみると、ちょっと不思議ですよね。
今後、「spring」を使った言葉を耳にしたら、
どっちの意味だろう、と考えるよりも先に、
元気の良さやエネルギーなどのニュアンスを表しているのかな、
と想像した方が、早く理解できるかもしれません。