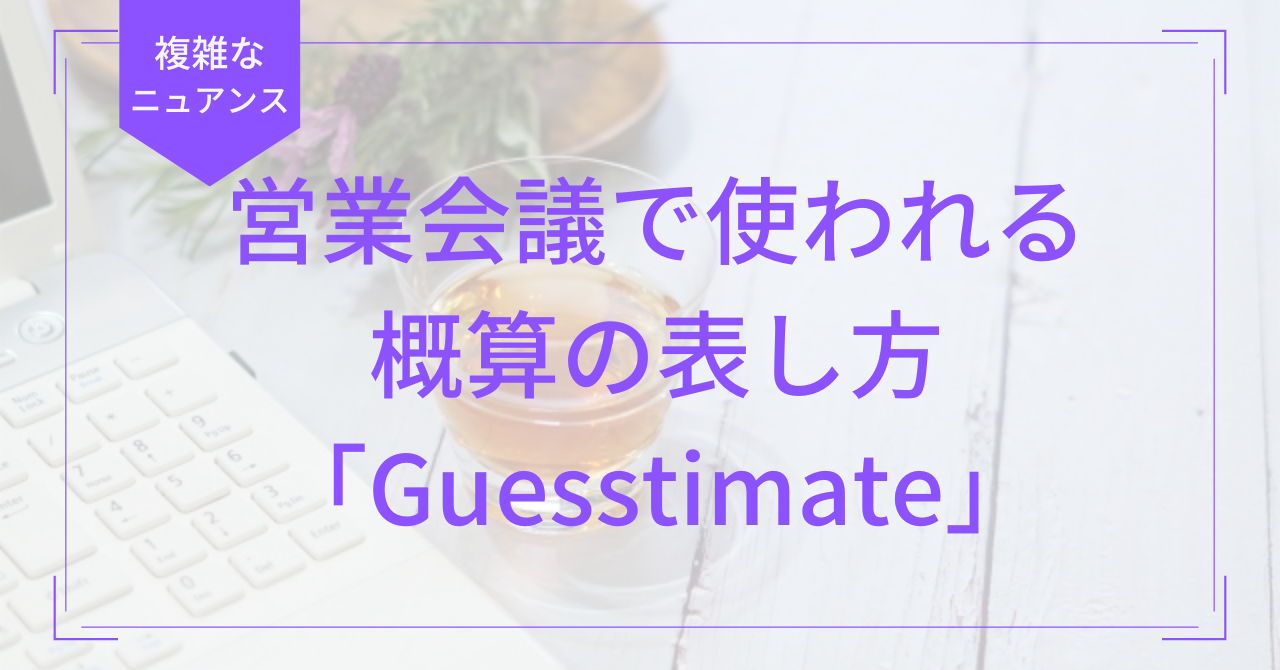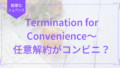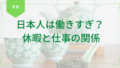営業関連の会議で、お金についての話をしているとき、
「ゲスティメイト(Guesstimate)」という言葉がよく使われます。
このワード、「guess(推測)」と「estimate(見積もり)」を組み合わせた造語なんですが、
どんな意味か分かりますか?
「推測+見積もり」で考えてしまうあと、
大体の数字、なんとなくの憶測、といったイメージが浮かびますが、
いわゆる、
「Give me a guess(えいやっ!の数字をください)」
とは少し違い、
「Give me a guestimate(ある程度の知識や経験に基づいた適切な見積もりをください)」
という意味があります。
理由はないけれどなんとなくの数字、ではなく、
その人の経験から想定される金額を算出し、提示してください、というこの言葉。
出てくる数値はざっくりではありますが、
計算に至るまでに論理的な推察、根拠があるため、会議の進行・決定へ大いに役立ちます。
それでは、
この「ゲスティメイト(guesstimate)」という言葉、
いったい誰が考えたのでしょうか?
語源を調べてみたところ、「guesstimate」は、
第二次世界大戦中のアメリカ軍で、すでに使われていたそうです。
考えてみればたしかに、戦場では、詳細なデータが取れない場面が多いと想像されます。
そんな中、素早い判断を求められるケースで、
経験に基づくざっくりとした計算(ゲスティメイト)は、重要な指標になりそうです。
外資系で働いていると、
同じような言葉で、「Back-of-the-napkin calculation(紙ナプキンの裏の計算)」
というフレーズを耳にする機会があります。
こちらは、そのまま訳すと「紙ナプキンの裏の計算」という意味ですが、
実際の使われ方も比較的似ています。
たとえば、コーヒーショップで商談をしているとき、
そこにあった紙ナプキンの裏に手早くメモを書いて計算するような場面、ありますよね。
それと同じニュアンスで、「その場でさっと計算する」
というニュアンスを伝えたいときに使用されます。
「Guesstimate」との違いとしては、
「Guesstimate」が データが少ない中で考える「直感的な見積もり・推測」であるのにたいして、
「Back-of-the-napkin calculation」 は、ざっくりした計算だけど、
一応数字に基づいている概算、というイメージです。
どちらも大雑把な計算でがあるのですが、
「Guesstimate」はより「勘」に近い感じ。
「Back-of-the-napkin calculation」は、ちょっとした計算が伴う場合、
といった感じで使い分けると、意図が通じます。
この違いが分かっていると、相手がこの発言をしている際に、
どのくらいの計算を求められているのか、というレベルを判断できて便利です。
売上予測や予算計画、リスク評価などの分野では、
前にも少し触れたことのある
「ボールパークフィギュア(Ballpark Figure )」という言葉も使われます。
野球場の観客数を、視覚的にだいたい判断する、というのが語源で、
こちらも概算や見積もり計算の表現です。
「Guesstimate」と「Ballpark Figure」
どちらも、「ざっくりとした見積もり・概算」という意味ですが、
この二つも若干、ニュアンスに違いがあり、注意が必要です。
「Ballpark Figure」は、ある程度のデータ・経験をもとにした大まかな見積もり。
「Guesstimate」は、データがなくても、とりあえず考えて出した概算。
となります。
似ているようで、出てくる計算結果の信頼度が大きく変わるため、
覚えておくとトラブルを未然に回避できます。
最終的な受注予想が「Guestimate」になるのは仕方ないですが、
会議で出てくる年間売り上げなどは、過去データがある部分。
勘ではなく、「Ballpark Figure」で提示してほしいものです。