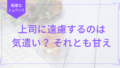ビジネスの場面でも日常会話でも、お金にまつわる慣用句は、日ごろから多く耳にします。
例えば、映画で耳にした “Cash is king”(現金が王様)というフレーズや
“Money talks”(金がモノを言う)などのフレーズは、よく知られています。
これらの言葉は、ちょっと頭の中で想像すれば、日本人でもなんとなく意味が掴めると思います。
ところが今回 “Green money”という表現を聞いて
「緑のお金?」とさすがに意味が分からず、調べてみました。
実際に使われていたのは、
- “This deal won’t count toward quota, but green money is money.”
という言い回しで、日本語に訳すと、
- 「この取引は営業実績には考慮されないけど、現金が入るならそれで良いじゃない」
というニュアンスになります。
Green Money=実際に動くお金、という意味合いで使われています。
このGreenですが、米ドル紙幣の「緑色」に由来しているそうです。
日本で言う「ゲンナマ」に近いような、生々しい印象がありますね。
他にも、Money talks(金がモノを言う)というのもよく聞く表現です。
- “They say values matter, but at the end of the day, money talks.”
- 「価値観が大事だとは言うけれど、結局のところ、お金がモノを言うのさ。」
という風に、やや皮肉の込もった、現実的な場面で用いられます。
「結局はお金が人や状況を動かす」という意味合いですね。
予算の話や、金額の影響力に触れたい場面で、聞く機会が多い気がします。
英語には、Cash is king (現金がいちばん強い)という言葉もあります。
- “In a crisis, cash is king.”
- 「危機の時こそ、現金がものを言う」
といった使われ方をするフレーズで、
景気が不安定な時期や不況下でよく使われます。
個人も会社も、いざという時にすぐ使える現金がなければ何もできません。
現金を持つ大切さ、資金繰りの重要性などを、端的に表しています。
とはいえ近年は、世界中でキャッシュレス比率が増えています。
2025年のデータでは韓国は99%、中国は83.5%がキャッシュレス決済になっているそうです。
中国へ旅行に行った知り合いに聞いたのですが、
アリペイやウィーチャットペイといったQRコード決済サービスが、
店舗での支払いはもちろん、公共料金の支払いや個人間の送金などに活用されているそうです。
日本でも最近は、QRコード決済やスマホ決済で、
税金や公共料金の支払いができるようになってきましたが、
それでもキャッシュレス比率としてはまだ4割程度とのこと。
ですが中国ではすでに、
現金を使うのは外国からの旅行者だけという状態になっているそうで、
現金で支払おうとすると、怪しまれたり、
場合によっては断られたり、というケースもあるそうです。
今後もキャッシュレス化が進んでいくと言われる時代。
Cash is kingという言葉が通じなくなり、次第に風化していくかもしれませんね。